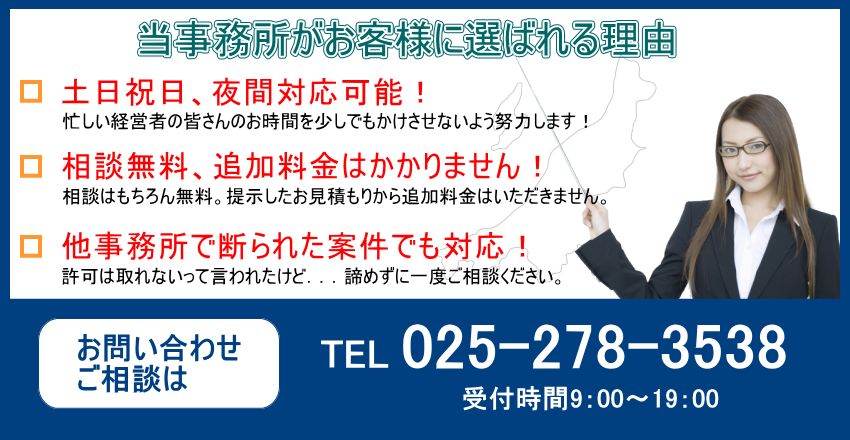- 欠格要員に該当しない
-
法人にあっては法人・役員、個人にあっては事業主・支配人、その他支店長、営業所長、法定代理人(営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者に対する方)が次のA~Fの欠格要件に該当するときは、許可は受けられません。
A 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない方
B 不正行為により建設業の許可を取り消されて5年を経過しない方
C 不正行為による建設業許可の取り消し手続が開始された後、廃業届を提出した方で、提出した日から5年を経過
しない方
D 建設業の営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない方(法人、個人事業主のみ該当)
E 許可を受ける業種の建設業について営業を禁止されており、その期間が経過しない方
F 次に掲げる方で、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない方
・禁固以上の刑に処せられた方
・建設業法に違反して罰金以上の刑に処せられた方
・建築基準法、宅地造成等規制法、景観法、都市計画法、労働基準法、職業安定法及び労働者派遣法のうち政令で定
めるものに違反して罰金以上の刑に処せられた方暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反したことにより、又は刑法(傷害罪・現場助勢罪・暴行罪・凶器準備集合罪・脅迫罪・背任罪)や暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金刑に処せられた方
許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は、重要な事実の記載が欠けているときは、許可は受けられません。
- 請負契約に関して誠実性がある
-
「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為をいいます。
「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為をいいます。
法人、法人の役員、個人事業主、支配人、支店長、営業所長、法定代理人が、建築士法、宅地建物取引業法等の規定により不正又は不誠実な行為を行ったことをもって免許等の取消処分を受け、その最終処分の日から5年を経過しない者である場合原則としてこの基準を満たさないものとして取り扱われます。
- 財産的基礎または金銭的信用を有している
-
【一般建設業の場合】
一般建設業の許可取得の場合、請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこととして、以下いずれかに該当することが求められます。・自己資本の額が500万円以上であること
・直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること
・500万円以上の資金調達能力を有すること
500万円以上の資金について取引金融機関が発行する預金残高証明書(残高日から2週間以内)
融資証明書(申請直前1か 月以内)【特定建設業の場合】
特定建設業の許可取得の場合、発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が政令で定める金額(8,000万円)以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有することとして、以下全てに該当することが求められます。・欠損の額が資本金の20パーセントを超えていないこと
・流動比率が75パーセント以上であること
・資本金が2,000万円以上で自己資本が4,000万円以上であること
※ なお、経営再建中の方については、更新に限り、特例措置を受けることができます
- 経営業務の管理責任者がいる
-
建設業の経営は他の産業の経営とは著しく異なった特徴を有しているため、適正な建設業の経営を期待するためには、建設業の経営業務について一定期間の経験を有した者が最低でも1人は必要であると判断され、この要件が定められたものです。
なお、具体的な要件は、以下のとおりです。
許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうちの1人が、個人である場合には本人または支配人のうちの1人が次のいずれかに該当することが必要であり、これらの者を経営業務の管理責任者といいます。
(イ)許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
(ロ)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
(ハ)許可を受けようとする建設業に関し、経営業務管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有していること。
(a)経営業務管の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
(b)7年以上経営業務を補佐した経験*(参考) ここでいう法人の役員とは、次の者をいいます。
・株式会社又は有限会社の取締役
・委員会設置会社の執行役
・持分会社の業務を執行する社員
・民法の規定により設立された社団法人、財団法人または協同組合、協業組合等の理事
*上記(ハ)により、申請(変更を含む。)をしようとする場合は、準ずる地位に該当するか否か個別ケースごとに審査が行われることになりますので、許可行政庁にお問い合わせ下さい。→ 許可行政庁一覧表へ
経営業務の管理責任者の設置は許可要件のため、例えば、許可を取得した後に経営業務の管理責任者が退職し、後任が不在となった場合は要件欠如で許可の取消し(建設業法第29条第1項第1号)となります。このため、このような不在期間が生じないよう、あらかじめ上記要件を満たす者を選任するなど、事前に準備しておくことが必要です。 - 専任技術者が営業所ごとにいる
-
営業所ごとに、建設工事の施工に関する一定の資格又は経験を有する技術者で専任の方をおかなければなりません。
専任の方とは、その営業所に常勤して専ら職務に従事することを要する方をいい、次に掲げるような方は除きます。・住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり常識上通勤不可能な方
・他の営業所における専任の技術者になっている方
・建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引主任者等他の法令により特定の事務所において専任を要すること とされている方(ただし、建設業において専任を要する営業所と他の法令により専任を要する事務所が同一企業で同一 場所である場合を除きます)
・他に個人営業を行っている方、他の法人の常勤役員である方等他の営業について専任であると認められる方許可を受けようとする業種の工事について
「一般建設業」
イ 高等学校若しくは中等教育学校(所定学科)卒業後5年以上、大学若しくは高等専門学校(所定学科)卒業後3年以 上の実務経験を有する方
ロ 10年以上の実務経験を有する方
(一部の業種に限り実務経験の緩和有り)
ハ イ又はロと同等以上の知識、技術、技能を有すると認められた方
(二級建築士、二級土木施工管理技士等)「特定建設業」
イ 国土交通大臣が定めるものにかかる試験に合格したもの、又は免許を受けた方
(一級建築士、一級土木施工管理技士等)
ロ 法第7条第2号(左記イ、ロ、ハ)のいずれかに該当し、かつ元請として4,500万円以上(消費税及び地方消費税を含む)の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する方
ハ 国土交通大臣(旧建設大臣)がイ又はロに掲げる方と同等以上の能力を有するものと認定した方
※ ただし、指定建設業(土、建、電、管、鋼、ほ、園)については、イに該当する方又はハの規定により国土交通大臣(旧建設大臣)がイに掲げる方と同等以上の能力を有するものと認定した方